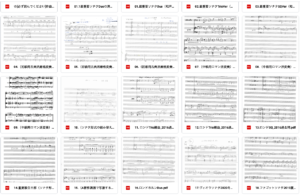芸大・音大受験のすすめ
AI作曲や発展した音楽制作ソフトで
誰しもがそれなりに作曲できてしまうこれからの時代こそ
どういった経歴で、どういった勉強をした人か?
長い歴史を持った音大出身なのか?
作曲した曲を発表するにしても、教えるにしても
その人がどういった人か?
(人物性・経歴・価値観・判断基準など)
がとても重要になってきます。
⚬藝大作曲科に入るには?
東京芸術大学 作曲科 実技について
・第一次試験
和声:Sop.課題とBass.課題の対策として
『和声―理論と実習 (1)』『和声―理論と実習 (2)』『和声―理論と実習 (3)』
『和声―理論と実習 (別巻)』『和声の進め方*』を使います。
初実施後の範例の詳細な分析と視奏に重きをおいています。(*作曲ドライブ内テキスト)
(各画像をクリックするとAmazon.co.jpなどにリンクします)
さらにこれらの教科書の文章をわかりやすくしたり
禁則と最適配置の補足説明
課題量の調節をして効率よく学習するために
作曲ドライブ内の『和声の進め方(随時更新)』を参考にしてください。
-300x221.png)
(レッスン生とスコアシェアコースメンバーは、上の画像をクリックすると作曲ドライブ内ドキュメントにリンクします)
『和声―理論と実習 (3)』 に進んだら並行して
『新しい和声──理論と聴感覚の統合』や『シャラン』などのフランス和声課題も研究していきます。
(各画像をクリックするとAmazon.co.jpなどにリンクします)
『和声―理論と実習 (3)』と『新しい和声──理論と聴感覚の統合』は
章により学習内容が重なる部分があるため
並行して学ぶ方法を『和声の進め方(随時更新)』
書いていますので参考にしてください。
『和声―理論と実習』が実施し終えたら
藝大作曲科第一次試験(和声)対策として
『和声課題50選 著者レアリザシオン篇と課題篇』
『和声課題集成』
「和声―理論と実習」の文章が読みにくいと思われる方は副読本として
「明解 和声法〈上巻〉―音楽を志す人々のために (音楽講座シリーズ 2)」をおすすめしています。
禁則の説明が丁寧です。
・第二次試験
対位法:厳格対位法とバッハ様式のコラール対策として
厳格対位法は
『厳格対位法 第2版 パリ音楽院の方式による』
ギャロン・ビッチュの『対位法』
『厳格対位法の進め方』を使用します。
対位法の範例写譜より始め
二声対位法から三声の華麗・混合類対位法の習得を目標に学んでいきます。


厳格対位法の効率の良い学習の進め方は
『厳格対位法の進め方』を参考にしてください。
-300x221.png)
(レッスン生とスコアシェアコースメンバーは、上の画像をクリックすると作曲ドライブ内ドキュメントにリンクします)
バッハ様式のコラールは
『バッハ様式によるコラール技法: 課題集と60の範例付き』と
『バッハ, J. S.: 371の四声コラール集 BWV 253-438/ブライトコップ & ヘルテル社/オルガン譜』
『バッハ様式のコラールの進め方(随時更新) 』を使います。


実際のバッハのコラールを分析しつつ課題を実施していきます。
象徴音型や詩と和声との関連性についても共に学んでいきます。
バッハ様式のコラールの効率の良い学習の進め方は
『バッハ様式のコラールの進め方(随時更新) 』を参考にしてください。
--300x217.png)
(レッスン生とスコアシェアコースメンバーは、上の画像をクリックすると作曲ドライブ内ドキュメントにリンクします)
・第三次試験
作曲:ソナタ形式、変奏曲、ロンド形式、ロンドソナタ形式などの対策として
実際にある様々な方法で書かれている楽曲を参考にし
作曲するとなると膨大な時間がかかるため
合格水準の要点を満たした学習ソナタ等
(過去問題実施例)を基準としてまねて学びます。
ソナタ・変奏曲・ロンド形式モデル曲の写譜やアレンジを主に課題として行います。
また今後作曲活動をしていくための必要な教養として
実際のルネサンス・バロック・古典派・ロマン派・近代・20世紀・現代にいたる名曲を
講師が持っている「楽曲分析された楽譜」を使って解説していきます。
実際の楽曲を分析する際も
学習ソナタ等の基準が手助けになります。
学習の手順は『作曲モデルの使い方と解説』を読んでください。

(レッスン生とスコアシェアコースメンバーは、上の画像をクリックすると作曲ドライブ内ドキュメントにリンクします)
下記画像をクリックすると大きい画像にリンクします。
シェアする全形式のモデル曲例
シェアする楽曲分析された楽譜のジャンル
・最終試験(ソルフェージュ・初見視奏・楽典など)
初見視奏 〜
20歳からピアノを始め3年ほどで私立音大に合格し
その後東京藝術大学に入学した経験から
効率の良いピアノの練習方法や曲選び
特に初心者のピアノレッスン受講の心構えや
先生選びなどをアドバイスしていきます。
ソルフェージュ 〜
自身の音感のタイプ(長所と弱点)*を理解した上で
効果的な方法を考えアドバイスしていきます。
*例えば弦楽器の方はポジションの関係で弾きにくい三全音=増4度が苦手だったり、トロンボーンの方は半音階が苦手だったり、ピアノ専攻の方は黒鍵がすべて♯に聴こえたりと。
また触れている楽器の影響で苦手な音程と調性があるため
そういった弱点を克服できるようアドバイスします。
楽典〜 学習段階に応じて教科書を選び教えていきます。詳しくは楽典・ソルフェージュレッスンコース
をご参考ください。
個人差はありますが1年半〜2年で東京芸術大学作曲科の受験水準に到達するようカリキュラムを組んでいます。
レッスンのお問い合わせについて
オンラインレッスンをご希望の方は下記ページからお問い合わせください。(クリックするとリンクします)
全国オンライン作曲レッスン